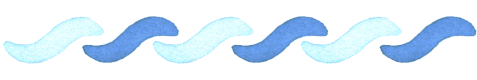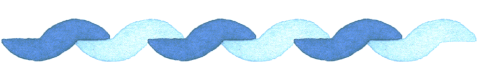花粉症
花粉症(アレルギー性鼻炎)でお悩みの方へ
早めの治療が肝心
花粉症は、鼻水、鼻づまり、くしゃみを主症状とするアレルギーです。花粉症でお悩みの方はお気軽にいらしてください。お薬によっては早めに開始することで、より症状が抑えられるものがございますので、お早めのご相談をお待ちしております。
花粉症の原因
花粉症は主に次の3つの原因に分けられます。
- スギ花粉症
- スギ以外の花粉症
- 多年草アレルギー
とくにスギ花粉症は10代以降の3人に1人の方にみられ(※1)、年々増加傾向にあります。その3つは種類さえ違いますが、お薬での治療は同様です。
花粉症の治療薬
当院では耳鼻科で行われている手術療法(鼻粘膜焼灼術など)は行わないため、内服・点鼻・点眼による治療がメインとなります。次のうちのいずれか、または複数を組み合わせて治療していきます。主な花粉症薬をお示しします。
抗ヒスタミン薬
-
内服薬
フェキソフェナジン(アレグラ®)
ロラタジン(クラリチン®)
オロパタジン(アレロック®)
レボセチリジン(ザイザル®)
など
点眼薬
オロパタジン(パタノール®点眼液)
エピナスチン(アレジオン®点眼液)
マスト細胞安定剤(マスト細胞脱顆粒抑制作用)
-
点鼻薬
クロモグリク酸 (インタール®点鼻液)
点眼薬
クロモグリク酸 (インタール®点眼液)
ロイコトリエン受容体拮抗薬
-
内服薬
モンテルカスト(シングレア®・キプレス®)
ステロイド
-
点鼻薬
フルチカゾン(フルナーゼ®点鼻液)
妊娠中・授乳中の方
安全に使えるロラタジンを処方しております。
運転をする方
より脳への移行性が少なく(※2)、眠くなりにくいフェキソフェナジンをおすすめしております。
お子さま
クロモグリク酸の点鼻・点眼は全身に吸収されず、副作用がないため、お子さまや妊娠されている方もお使いいただきやすいお薬ですが、使い始めてから効果が出るまでに、おおよそ2週間ほどかかるため、早めに開始することが重要です。症状に応じて抗ヒスタミン薬を使います。
当院での抗ヒスタミン薬の処方について
当院では上記以外の薬剤については、安全性・有効性・経済性が確立されている上記薬剤を上回るものでないと判断し、採用がございません。上記以外のお薬をご希望される方は院外処方となりますため、ご相談ください。
当院での花粉症治療
2歳未満の方
必要に応じて抗ヒスタミン薬内服やクロモグリク酸の点鼻を用います。点鼻が難しい場合はロイコトリエン受容体拮抗薬の内服も考慮します。
2歳以上〜成人の方
抗ヒスタミン薬内服、必要に応じてクロモグリク酸の点鼻を用います。また持続する強い鼻炎症状についてはステロイド点鼻を使います。ロイコトリエン受容体拮抗薬については点鼻が使えない方や喘息を合併している方におすすめしております。目の症状については点眼薬を使います。
ステロイド点鼻について
国際的なガイドラインにおいても、中等度から高度の鼻炎症状に対してステロイド点鼻は最も効果があるとされています(※3)。効果は数時間で出てきますが、最大の効果を発揮するまで数日から数週間と大きく個人差があるため、すぐに効果がみられない場合でも最初の1−2週間は辛抱強く使っていく必要があります。点鼻の後味・におい・刺激性などが気になる場合は、パウダータイプの点鼻もありますのでご相談ください(パウダータイプの点鼻は成人のみの適応です)。
よくあるご質問
ステロイドの点鼻は副作用がありますか?
ステロイドの点鼻は、内服で用いるステロイドの量と比べて僅かであり、また全身に吸収されにくいため、先行研究においても、ほぼ副作用がなく安全に使えるとされています。お子さまで連続2ヶ月以上使用する場合は、ごくわずかに身長などの成長が緩やかになる可能性があるとされ、ご希望される方には注意しながら使用していきます。
点鼻の使いすぎはよくない?
薬局で買える薬の中には、血管収縮薬が添加されているものがあります。鼻粘膜への血流をおさえ、むくみをおさえるため即効性があり、すぐに鼻通りがよくなるため、これらの点鼻を多用する方がいらっしゃいます。しかし連用によって鼻血が起こりやすくなったり、鼻粘膜が肥厚してきて、より鼻づまりがひどくなる薬剤性鼻炎をおこすことがあります。また、高血圧、不眠、イライラ感、頭痛などの副作用もあります。そのため血管収縮薬(テトラヒドロゾリン、ナファゾリンなど)が添加されている薬剤はおすすめしませんし、短期間でも使う際は注意が必要です。一方で当院で採用のある点鼻は、ステロイドとクロモグリク酸ナトリウムのみですので、このような薬剤性鼻炎を起こすことはありませんのでご安心ください。
レファレンス
- Okubo K, Kurono Y, Ichimura K, et al. Japanese guidelines for allergic rhinitis 2017. Allergol Int. 2017;66(2):205-219. doi:10.1016/j.alit.2016.11.001
- McDonald K, Trick L, Boyle J. Sedation and antihistamines: an update. Review of inter‐drug differences using proportional impairment ratios. Hum Psychopharmacol Clin Exp. 2008;23(7):555-570. doi:10.1002/hup.962
- Dykewicz MS, Wallace DV, Amrol DJ, et al. Rhinitis 2020: A practice
parameter update. J Allergy Clin Immun. 2020;146(4):721-767. doi:10.1016/j.jaci.2020.07.007