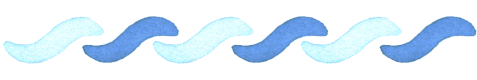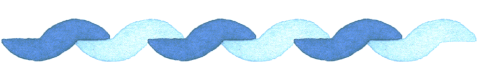インフルエンザ
インフルエンザ接種ご予約
毎年、10月にインフルエンザワクチンの接種がスタートします。接種後、2−4週間で十分な予防効果が得られ、効果は4ヶ月程度続きます。
注意事項
インフルエンザワクチン接種にはご予約が必要です。
なお、インフルエンザ予防接種の際に同時診察をご希望の際は、事前にご相談いただけますと時間を調整させていただきます。(事前のご相談なしの同時診察は混雑時はお断りすることがございます。)
インフルエンザは3タイプに分けられます
インフルエンザにはタイプがあり、大きくA型・B型・C型の3タイプに分けられます。症状などに違いがあり、流行しやすいのはA型とB型です。A型とB型は重症化リスクも高いので、ワクチンはこの2タイプに効果があるようにつくられています。
1A型インフルエンザ
最も症状が強く、毎年多くの方が感染します。変異を起こしやすいため、世界的な流行を起こす可能性が高いタイプです。主な症状は、38度以上の高熱が出て、のどの強い痛み・筋肉痛などを起こします。重症化によってインフルエンザウイルスによる脳症や肺炎を合併することがあります。
2B型インフルエンザ
以前はB型の流行が数年ごとに起こっていましたが、現在は毎年のように流行するようになってきています。流行がはじまるのはA型よりも遅く、春に近付くと患者数が増加します。消化器系の症状を起こすことが多く、嘔吐・腹痛・下痢などがある場合B型が疑われます。
3C型インフルエンザ
軽症のまま治るため、感染しても気付かないケースがかなり多く、流行することもほとんどないタイプです。
注意が必要なインフルエンザ
A型インフルエンザには、強毒性の鳥インフルエンザや豚インフルエンザ、そして新型インフルエンザなどが含まれています。重症化率・致死率の高いものがありますので、その年の流行を見ながら対応していきます。
予防接種を受ければ感染しない?
予防接種を受けてもインフルエンザ感染を100%防ぐことができるというわけではありません。体力が低下している・免疫力が落ちている場合には、予防接種を受けても感染してしまいます。ただし、予防接種を受けていると感染した場合も重症化を防ぐことができます。重症化を防ぐことも予防接種の重要な役割です。
インフルエンザを予防するために
インフルエンザは飛沫感染と接触感染を起こします。飛沫感染は、感染者の咳などで飛ばされた細かい飛沫によって感染します。接触感染は、ウイルスが付着したものに触れた指で口などの粘膜を触ってしまって感染します。こうしたことから、インフルエンザの予防には、マスクとこまめな手洗いが有効です。手洗いの際にはよく泡立てた石けんで手指から手首までのすみずみをしっかりこすって(20秒かけて)、水道水できれいに洗い流し、乾いたタオルやペーパータオルなどで水気を拭き取ります。
インフルエンザになってしまった場合
発症してすぐであれば、ウイルスの増殖を防ぐ抗ウイルス薬による治療が有効とされています。48時間以内に熱が下がりはじめますが、発熱して5日、もしくは解熱した日を数えず2日(どちらか長い方)経過するまで、登園・登校・出社は控えてください。
治療薬
何種類かの抗ウイルス薬があります。当院ではおもに、オセルタミビル(タミフル)を用いています。当院で選択しているオセルタミビルは現時点で治療効果(治療・重症化の抑制)・安全性について他の薬と比較して、最もエビデンスのある薬剤です。
-
ノイラミニダーゼ阻害薬
-
経口薬
オセルタミビル(タミフル)
吸入薬
ザナミビル(リレンザ)
ラニラミビル(イナビル)
注射薬
ベラミビル(ラピアクタ)
-
キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬
-
経口薬
バロキサビル(ゾフルーザ)
特にリスクの高い5歳未満、65歳以上の方、妊娠中、産後2週間以内の方、施設入所中の方、それ以外でも基礎疾患のある方は、積極的に治療薬を使用します。発症した方全員に処方されるものではありません。
たとえば発症後48時間以上経過し、すでにウイルスが増殖してしまっている場合は、治療薬による効果が見込めないため経過を見ていくことが望ましいとされています。そのような場合は、症状に応じた対症療法を行います。